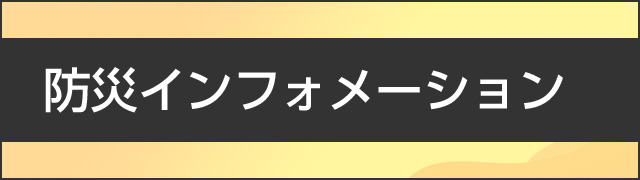ここから本文です。
1.原子力災害を知るために
このコーナーでは、原子力発電所で発生する原子力災害に備えるために、皆さんに知っていただきたいことがらを掲載しています。放射線や被ばく、避難の仕組みなど、正しく知って原子力災害に備えるための参考としてください。
<このコーナーを、冊子の形で印刷できます>
原子力防災のしおり1「原子力災害を知るために編」(PDF:891KB)(別ウインドウで開きます)
冊子(A4サイズ)の形で印刷するためのPDFです。図表やイラスト、写真などの表現やレイアウトがホームページと異なる場合があります。
原子力災害と放射線
原子力災害とは何ですか
原子力発電所の事故により、発電所から放射性物質が外にもれてしまうことをいいます。原子力災害は、自然災害と比べ、主に次のような特徴があります。
- 放射性物質は、放射線を放出しながら雲のようなかたまり(「プルーム」と呼ばれます)となって風下へ広がります。
- 放射性物質や放射線は人間の五感で感じることができませんが、放射線測定器で検知することができます。
- 放射線による被ばくから身を守るためには屋内退避や避難などの対応(防護措置)が必要となります。
<放射性物質の放出とブルーム>
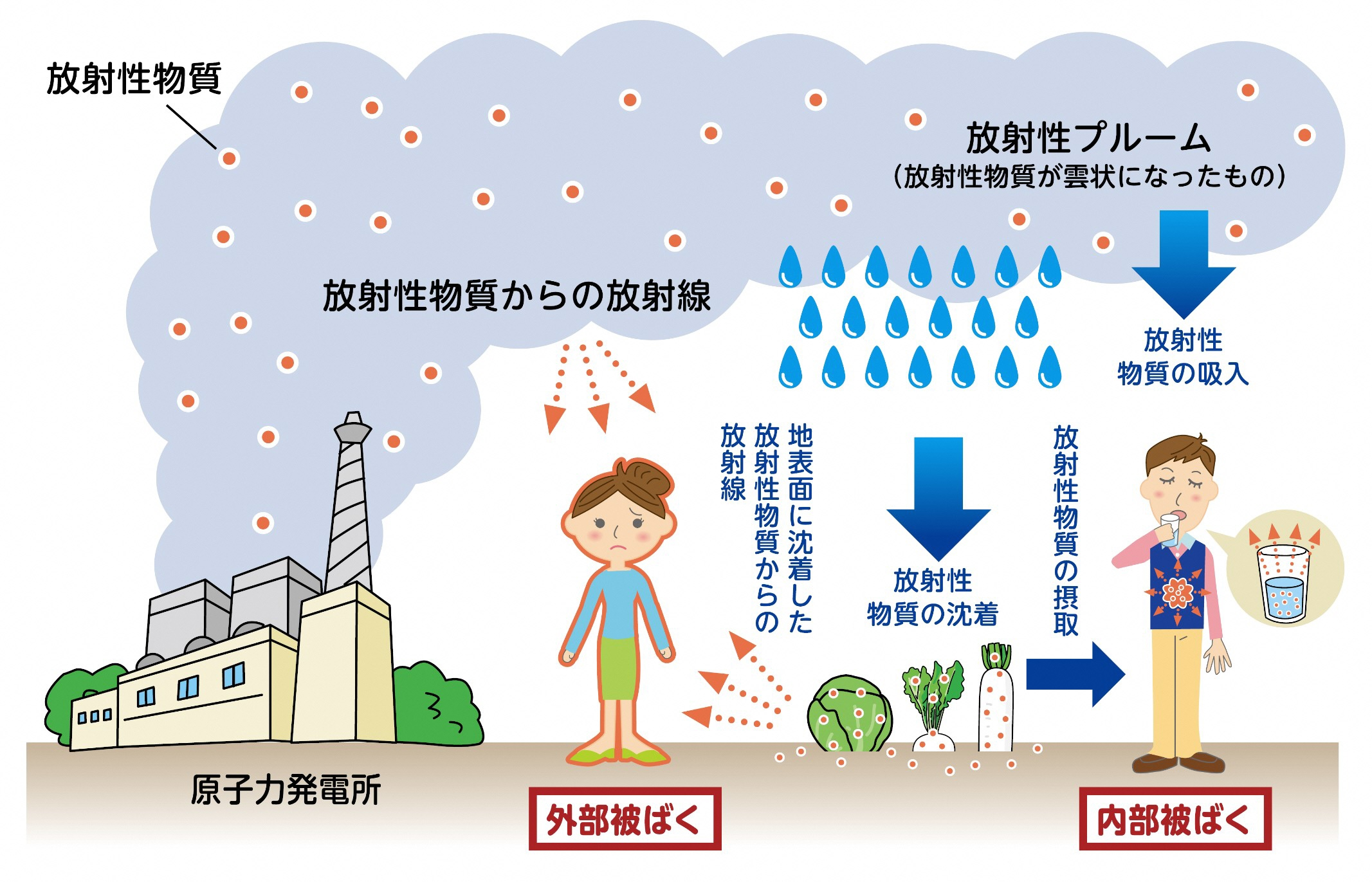
放射線と測定
物質から飛び出るエネルギーを持った粒子などを「放射線」と呼びます。この放射線を出す物質のことを「放射性物質」、放射線を出す能力を「放射能」と呼びます。
粒子線や電磁波である「放射線」は、五感に感じることもなく、目に見えず、匂いや味もしません。
五感で感じることができない放射線ですが、専用の測定機器でその量を測ることができます。また、測定の内容ごとに単位が付けられています。
Sv(シーベルト)被ばく線量
人が放射線を受けることを「被ばく」といいます。この時の人体への影響を表す単位です。また、空間の1時間当たりの放射線の量を表す単位をSv/h(シーベルト・パー・アワー)「空間放射線量率」と呼びます。
Gy(グレイ)吸収線量
放射線が物質などにあたった場合、「エネルギー」がどれだけ物質に吸収されたかの量を表す単位です。
Bq(ベクレル)放射能の単位
放射性物質が放射線を出す能力(放射能)の強さを表す単位です。単位重量や単位面積当たりの放射能を表すには、1kgの物質のときは「Bq/kg」と表します。
日常生活と放射線
私たちは、普段の生活の中でも放射線を浴びています。
日常生活の中では、宇宙から飛んでくる放射線や、大地や食物などに含まれる自然放射性物質からでる「自然放射線」を受けています。この放射線の量は、日本平均では年間一人当たり約2.1mSvと見積もられています。
また、この自然放射線とは別に、人工的な放射線を利用することにより放射線を受けることもあります。この「人工放射線」には、医療の診察や治療でのレントゲンやCTスキャンなどがあります。
これらの日常生活で浴びるくらいの放射線の量では、健康に影響が出ることはありません。
<身の回りの放射線>
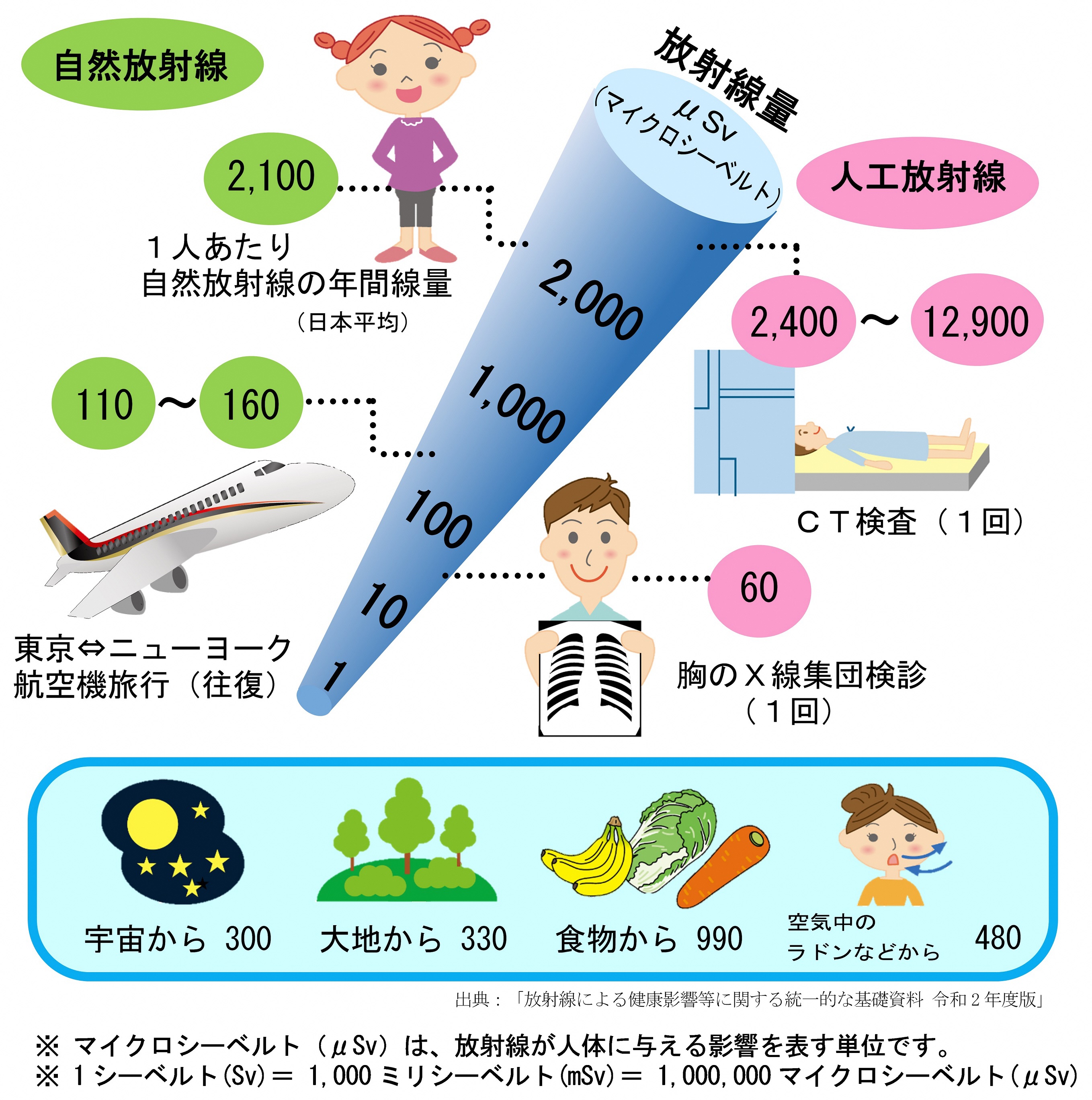
被ばくを防ぐために(放射線の性質)
外部被ばくを防ぐ
距離による防護
放射線の強さは、放射性物質から離れれば離れるほど弱くなる性質を持っています。これは、電球の光に例えたとき、近くが明るく、遠くなると暗くなるのと同様です。このため、原子力災害のときには、「距離による防護」として、遠くに避難します。
遮へいによる防護
放射線は物質を通り抜ける性質がありますが、放射線の種類によってその強さが違います。α線(アルファー線)は紙1枚で、β線(ベータ線)はアルミニウムなどの薄い金属で止まります。γ線(ガンマ線)とX線(エックス線)を止めるには鉛や鉄の厚い板が必要です。このため、放射性物質の飛散の恐れがあるときには、「遮へいによる防護」として、まずは屋外から建物などの屋内に退避します。
時間による防護
放射線の被ばく線量は、時間に比例して大きくなります。このため、「時間による防護」として、被ばくする場所にいる時間を短くすることが大切です。
内部被ばくを防ぐ
放射線に汚染された物が身体の中に入ると内部被ばくがおこります。このため、汚染された物の飲食に注意します。また、鼻から吸い込まないようにマスクなどを着用して防ぐことが大切です。
体表面の汚染を防ぐ
皮膚など身体の表面に放射性物質が付着することを防ぐことが大切です。このため、避難するときなどは、皮膚がなるべく表に出ないように長袖や雨ガッパ、帽子などを着用してください。
原子力災害が発生したら
原子力発電所で万が一、原子力災害が発生したときには、放射線からの被ばくを防ぐための行動をすることになります。しかし、被ばくを防ぐための対策(防護措置)は、災害の状況などによってその対処法が違ってきますので、状況に合わせた適切な行動をすることが大切です。
情報収集と判断の種類
原子力災害の場合は、避難などといった防護措置の判断基準があらかじめ定められています。この基準は、原子力発電所の状態や、放射線の測定結果(緊急時モニタリング結果)などを基に、国の原子力規制委員会が判断し、県や市が避難などの指示を出します。このため、国や県、市などから発信される情報に注意してください。
市では、同報無線や公式ライン、防災メールなどのさまざまな情報発信手段を使って、事故の情報などをお知らせします。
<発電所の状況に基づく判断基準>
| 発電所の状況(判断の基準) | 緊急事態区分 | UPZ内(焼津市全域)の対応 | ||
| 放射性物質の放出前 | 放射性物質放出前 (例) 御前崎市で震度6弱以上の地震が観測された時など |
警戒事態 | 発電所事故の警戒情報が発信されます 情報の入手に努めてください |
|
|---|---|---|---|---|
| 放射性物質放出の恐れ (例) 全交流電源が喪失した状態が継続した時など |
施設敷地緊急事態 | 屋内退避準備の情報が発信されます 屋内に退避する準備を進めてください |
||
| 放射性物質放出の可能性が高まった場合 (例) 原子炉を冷却する全ての機能を喪失した時など |
全面 緊急事態 |
屋内退避 | 屋内退避の指示が発信されます 自宅などで屋内退避する 避難の準備を進める |
|
| 放射性物質の放出後 | (放射線モニタリングの値) 空間放射線量率:500μSv/h 超過 |
避難 | 区域を選定し、速やかに市外に避難するよう指示 (1日以内を目安) |
|
| (放射線モニタリングの値) 空間放射線量率:20μSv/h 超過 |
一時移転 |
区域を選定し、 市外に一時移転の指示 |
||
屋内への退避(放射性物質の放出前)
原子力発電所で事故が発生したとの情報があったら、不要不急の外出を控えてください。自宅などで引き続き情報収集に努めます。放射性物質との接触を避けるための手段として、屋内に退避ことが効果的ですので、そのための準備を進めます。
また、放射性物質を放出する恐れのある情報があった場合には、すみやかに屋内退避をします。自宅や近くの建物の中に入り、ドアや窓を閉めて、外気との接触をしないようにしてください。
市外への避難(放射性物質が放出されたら)
原子力発電所から放射性物質が放出された後には、住んでいる地域の放射線の量(空間放射線量率)によって対処方法が違ってきます。県や市からの新たな指示が出るまでは、引き続き屋内退避を続けてください。
放射線の量が定めた基準を超えたときは、市外に避難や一時移転をします。焼津市では、避難先や避難方法を「焼津市原子力災害広域避難計画」で定めています。
避難先は、浜岡原子力発電所単独で事故が発生した時と、大規模地震などで広域的に被害が発生した複合災害の時とで、その場所が変わります。
避難先となる市町は、単独での事故の場合は県内東部の市町と神奈川県内に避難します。複合災害の場合は埼玉県内の東部市町に避難します。また、浜岡原子力発電所から遠く離れた親せきや知人宅に避難することもできます。
なお、避難の判断は市内を8つの区域に分けて行い、自家用車での避難が基本となります。
- 広域避難の詳細は、このホームページの「3.原子力事故が発生したら・広域避難計画」等をご覧ください。
<焼津市の広域避難のイメージ>
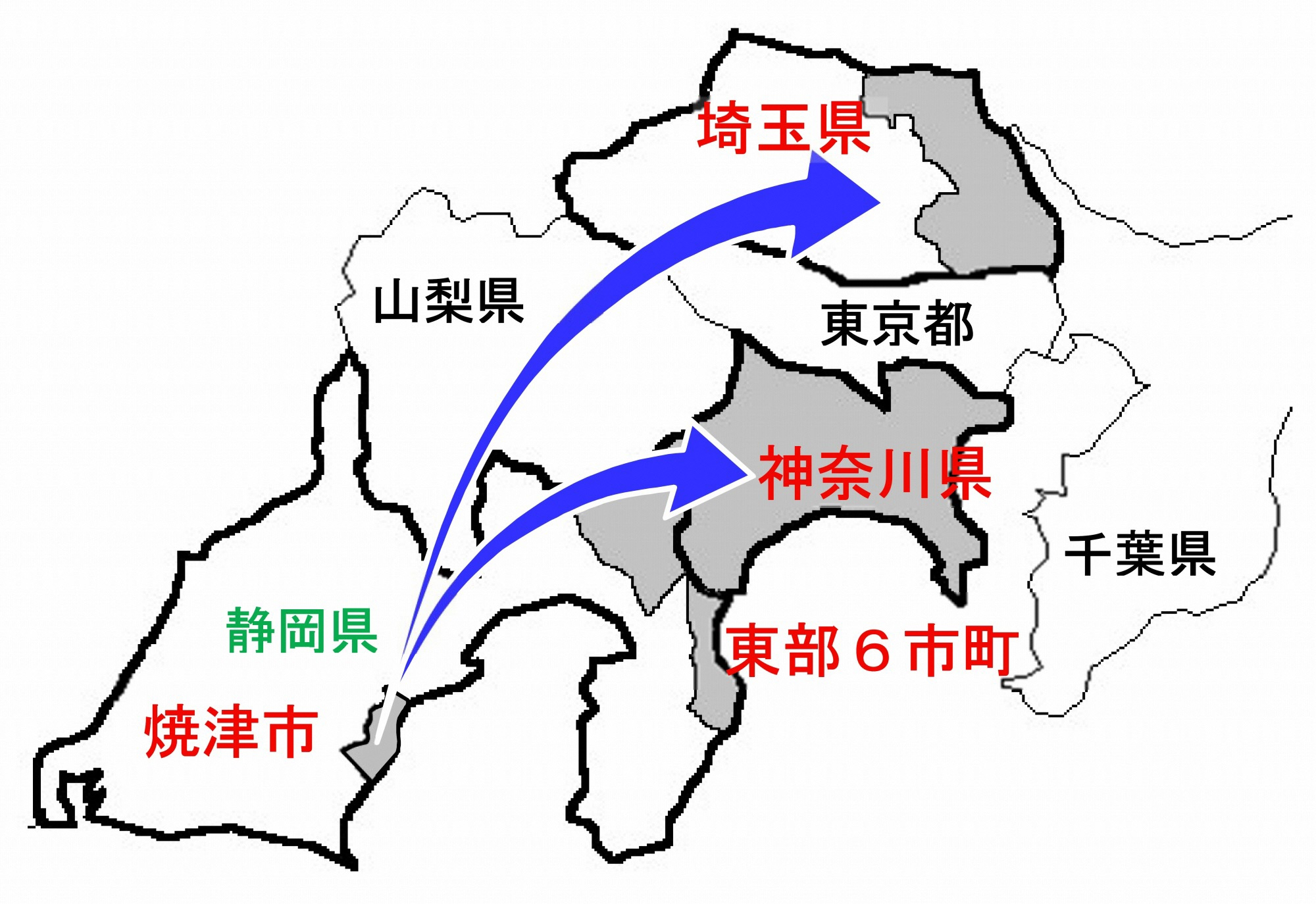
このページの情報発信元
ページID:14504
ページ更新日:2024年7月16日