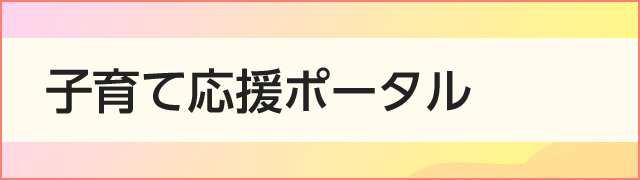ここから本文です。
子どもの予防接種
ページ内メニュー
予防接種する時の注意
予防接種は健康状態が安定している時に受け、その病原体の感染を予防するものです。必ずお子様の体調の最も良い時に受けてください。
接種時は必ず健康状態の分かる保護者が同伴してください。
詳しくは、生後1カ月半から2カ月頃までに伺う「こんにちは赤ちゃん訪問」の際に配布する「予防接種と子どもの健康」及び「予防接種手帳」をご覧ください。
ワクチン毎に接種対象期間やおすすめの接種時期があります
予防接種は予防接種法に基づいて実施しています。注意事項(月齢及び年齢、間隔、回数)を守り、かかりつけ医師と相談の上、予防接種を受けましょう。
異なる種類のワクチンを接種する場合、「接種間隔」が決まっています
- 注射生ワクチン【BCG・麻しん風しん混合(MR)・水痘・おたふく】は27日以上あけてから次の注射生ワクチン予防接種を受けてください。
- 不活化ワクチン【B型肝炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・五種混合・四種混合・二種混合(DT)・不活化ポリオ・日本脳炎・子宮頸がん予防・インフルエンザ】、経口生ワクチン【ロタ】は間隔の制限はありません。
定期予防接種
焼津市と藤枝市の委託医療機関で受けることができます。
定期予防接種委託医療機関についてはPDFファイルをご覧ください。
- 2024年度定期予防接種委託医療機関一覧(子宮頸がんワクチンを除く)(PDF:105KB)(別ウインドウで開きます)
- 2024年度子宮頸がんワクチン実施医療機関(PDF:74KB)(別ウインドウで開きます)
焼津市・藤枝市の委託医療機関以外で接種する場合は、事前に健康づくり課(保健センター)への申請が必要です。接種予定日の3週間前までには申請をしてください。
持ち物
- 母子健康手帳
- 予診票(予診票は「こんにちは赤ちゃん訪問」の際にお渡ししています。予診票がない場合は各医療機関または健康づくり課(保健センター)にて母子健康手帳で接種歴を確認の上お渡しします)
- 費用:対象期間内は原則無料(公費負担)で接種できます。
ロタウィルスワクチン
対象
- 1価(ロタリックス)…生後6週から生後24週0日までの子
- 5価(ロタテック)…生後6週から生後32週0日までの子
方法
- 1価(ロタリックス)…27日以上の間隔で2回接種
- 5価(ロタテック)…27日以上の間隔で3回接種
いずれのワクチンも、初回接種は生後14週6日までに行うことが推奨されています。
B型肝炎ワクチン
対象
- 生後2月以上生後12月に至るまでの間にある子
方法
- 27日以上の間隔で2回接種、さらに初回接種から139日以上の間隔をおいて1回接種(計3回)
ヒブワクチン
2024年4月1日に五種混合ワクチンが定期予防接種化されましたが、ヒブワクチン・四種混合ワクチンで接種を開始した場合は、原則同じワクチンで接種を完了してください。
対象
- 生後2月以上生後60月(5歳)に至るまでの間にある子で五種混合未接種者
方法
初回接種開始が生後2月から生後7月まで
- 初回接種:27日(医師が認める場合は20日)以上、標準的には56日までの間隔をおいて3回接種
- 追加接種:初回接種の3回目接種終了後7月以上、標準的には13月までの間隔をおいて1回接種
初回接種開始が生後7月の翌日から生後12月まで
- 初回接種:27日(医師が認める場合は20日)以上、標準的には56日までの間隔をおいて2回接種
- 追加接種:初回接種の3回目接種終了後7月以上、標準的には13月までの間隔をおいて1回接種
初回接種開始が生後12月の翌日から生後60月に至るまで
- 1回接種
小児用肺炎球菌
対象
- 生後2月以上生後60月(5歳)に至るまでの間にある子
方法
2024年4月1日に15価ワクチンが定期予防接種化され、13価と15価のワクチンがあります。原則15価ワクチンでの接種となりますが、13価ワクチンで接種を開始した場合は、13価ワクチンのまま継続することも可能です。
初回接種開始が生後2月から生後7月に至るまでの間
- 初回接種:27日以上あけて3回接種(生後12月までに完了)
- 追加接種:初回の3回目から60日以上の間隔をおいた後であって、生後12月に至った日以降に1回接種(生後12月~15月に至るまでの間)
初回接種開始が生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間
- 初回接種:生後12月までに27日以上あけて2回接種
- 追加接種:生後12月以降に、初回の2回目から60日以上あけて1回接種
初回接種が生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間
- 60日以上あけて2回接種
初回接種が生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間
- 1回接種
五種混合(百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎、ヒブ)
対象
- 生後2月~90月(7歳6か月)に至るまでの間にある子で、生ポリオワクチン・不活化ポリオワクチン及び三種混合ワクチン・四種混合ワクチン・ヒブワクチン未接種者
方法
- 1期初回…20日以上の間隔をおいて3回接種
- 1期追加…1期の3回目接種後、標準的には6月から13月までの間に1回接種
四種混合(百日せき、ジフテリア、破傷風、急性灰白髄炎)
2024年4月1日に五種混合ワクチンが定期予防接種化されましたが、ヒブワクチン・四種混合ワクチンで接種を開始した場合は、原則同じワクチンで接種を完了してください。
対象
- 生後2月~90月(7歳6か月)に至るまでの間にある子で生ポリオワクチン・不活化ポリオワクチン及び三種混合ワクチン・五種混合ワクチン未接種者
方法
- 1期初回…20日から56日までの間隔で3回接種
- 1期追加…1期の3回目接種後、標準的には12月から18月までの間に1回接種
二種混合(ジフテリア、破傷風)
対象
- 生後90月(7歳6か月)までに四種または三種混合1期を3回以上または二種混合1期を2回以上接種済みで、小学6年生から中学1年生までの誕生日の前日までの子
方法
- 2期…1回接種
BCG
対象
- 生後12月に至るまでの間にある子(標準的な時期:生後5月から8月まで)
方法
- 1回接種
麻しん(はしか)・風しん混合ワクチン
現在、国内での麻しんの流行が危惧されています。対象の年齢を迎えたら、はやめの接種をおすすめします。
対象
- 1期…生後12月(1歳)以上24月(2歳)未満
- 2期…5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間(幼稚園でいう年長児相当)
方法
- 1期、2期それぞれの対象期間内に1回接種
水痘
対象
- 生後12月から生後36月に至るまでの間にある子
方法
- 初回接種…生後12月から15月に至るまでに1回
- 追加接種…1回目の接種から6月から12月の間隔をおいて1回
日本脳炎
対象
- 1期…生後36月(3歳)から90月(7歳6か月)に至るまでの間にある子
- 2期…9歳から13歳未満で、1期を2回以上接種している子
方法
- 1期…6日~28日の間隔で初回2回、初回2回目から1年の間隔をおいて追加接種1回(計3回)
- 2期…1期3回目からおおむね5年後に1回接種
特例措置の対象について
第1期、第2期の日本脳炎ワクチンの接種は、2005年(平成17年)5月より、積極的接種勧奨を一部差し控えていましたが、2011年(平成23年)5月20日の法改正により、下記の通り特例措置ができました。
- 1995年(平成7年)4月2日から2007年(平成19年)4月1日生まれの人は、20歳の誕生日の前日まで不足分を公費負担で接種できます。
子宮頸がん予防ワクチン
平成25年度より積極的勧奨が差し控えられてきましたが、令和3年11月より積極的勧奨が再開となりました。他の予防接種と同様、有効性及び安全性について十分に説明を受け、理解された上で受けてください。子宮頸がんワクチンについて、詳細は「ヒトパピローマウィルス(子宮頸がん予防)ワクチンについて」をご覧ください。
対象
- 小学6年生~高校1年生相当の女子
ただし、積極的勧奨が差し控えられていた期間に定期接種の対象であった方は、令和7年3月31日までは定期接種として公費接種することができます。対象は平成9年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれの女子です。
(※)平成9年4月2日生まれから平成17年4月1日生まれの女子で、積極的勧奨が差し控えられていた間に自費接種された方は、費用の助成制度があります。詳細は、任意予防接種のページをご覧ください。
方法
原則として、同じワクチンで接種します。
組換え沈降2価ヒトパピローマウィルス(サーバリックス)
- 3回接種(2回目:1回目の接種から1月以上あけて、3回目:1回目の接種から6月以上あけて)
組換え沈降4価ヒトパピローマウィルス(ガーダシル)
- 3回接種(2回目:1回目の接種から2月以上あけて、3回目:1回目の接種から6月以上あけて)
組換え沈降9価ヒトパピローマウィルス(シルガード)
【小学校6年生~14歳】1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
- 2回接種(2回目:1回目の接種から6月以上あけて)
【15歳以上】1回目の接種を15歳になってから受ける場合
- 3回接種(2回目:1回目の接種から2月以上あけて、3回目:1回目の接種から6月以上あけて)
任意予防接種費用を一部助成します
お子様のおたふくかぜワクチン、インフルエンザワクチンの接種費用の一部助成が受けられます。接種日に焼津市民であることが条件です。
おたふくかぜワクチン
対象
- 生後12月(1歳)から生後24月(2歳)に至るまでの間にある子
- 小学校就学前の1年間(幼稚園でいう年長児相当)にある子
助成金額
- 1回につき2,000円(生活保護世帯は全額助成)
助成回数
- 1人各年齢ごとに1回ずつ計2回まで
インフルエンザワクチン
各シーズンの10月1日から翌年3月31日までに受けた接種が対象です。
実際に接種が行われる期間は、この期間内で、各医療機関によって異なります。
対象
- 中学3年生までの子
助成回数
- 小学生以下…1シーズンにつき2回まで
- 中学生…1シーズンにつき1回のみ
助成金額
- 1回につき1,000円(生活保護世帯は全額助成)
助成方法(おたふく・インフルエンザワクチン共通)
焼津市または藤枝市の協力医療機関で受ける場合
医療機関の窓口にて「任意予防接種(受領委任払)申請書」を記入し、接種費用と助成費用の差額を支払ってください。
持ち物
- 母子健康手帳
- 印鑑(シャチハタは不可)
- こども医療費受給者証など住所が分かるもの
- 生活保護世帯の場合は、福祉事務所が発行する「生活保護受給証明」
その他の医療機関で受ける場合
接種後に、健康づくり課(保健センター)の窓口にて「任意予防接種(償還払)申請書」を提出してください。審査の上、後日保護者の指定の口座へ助成額を振り込みます。
持ち物
- 接種者名が記載された領収書
- 接種の記録(母子健康手帳、予防接種済証、予診票の写しなど)
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 振込口座のわかる通帳(保護者名義のもの)など
- 生活保護世帯の場合は、福祉事務所が発行する「生活保護受給証明」
申請期間…接種後1年間
子宮頸がん予防ワクチン助成制度
令和3年度に子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨が再開となりました。その間に、定期予防接種の年齢を過ぎて自費接種された方に費用の助成をします。
対象
下記の1~3のすべてに該当する方
- 平成9年4月2日生まれから平成17年4月1日生まれの女子
- 2022年4月1日に焼津市に住所を有する方
- 子宮頸がんワクチンの2価(サーバリックス)または4価(ガーダシル)の接種をした方
申請期間
2022年9月1日から2025年3月31日まで
申請期日を過ぎた場合は、受け付けられませんので、ご注意ください。
助成方法及び助成回数
- 焼津市健康づくり課(保健センター)へ申請する。
- 1人上限3回までです。ただし定期接種をされている場合は、その回数を引いた回数を上限とします。
- 接種金額にかかわらず、一定金額を助成します。
- 審査の上、後日指定の口座(保護者または18歳以上は本人口座)へ助成額を振り込みます。
申請時の持ち物
- 接種者名・接種したワクチン内容・接種日が記載された領収書と接種の記録(母子健康手帳、予防接種済証、予診票の写しなど)またはそのどちらか
- 1のどちらもない場合は医療機関での証明書(第2号様式)(ワード:20KB)(別ウインドウで開きます)(ワード:20KB)
- 印鑑(シャチハタは不可)
- 振込口座のわかる通帳など(18歳以上は本人のもの)
- 申請書(窓口で記入)
(※)1.2のどちらかと3.4をお持ちください。2は医療機関により有料となる場合がありますが、その場合の発行にかかる費用は申請者負担となりますので、ご了承ください。
特別の理由による再接種が必要な方への接種費用の助成
20歳に達するまでの方で、定期予防接種後に骨髄移植手術等の病気治療により、予防接種の効果が期待できないと医師に判断され、任意で再度予防接種を受ける者の予防接種費用の助成を行います。該当される場合は、再接種を受ける前に健康づくり課にご相談ください。
助成内容
- 過去に定期予防接種として受けたワクチンの再接種費用(但し、焼津市で定める定期予防接種委託料を助成上限額とする。)
手続きの流れ
- 対象者認定申請をする(申請には主治医の意見書の提出が必要となります)。
- 医療機関にて再接種を受ける。
- 助成対象者が接種医療機関に全額を支払った後に、市に払い戻しの申請をする(償還払)。
このページの情報発信元
ページID:546
ページ更新日:2024年4月18日